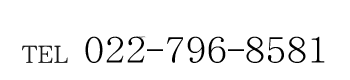ドライマウスの話
こんにちは。仙台かわすみ産業医事務所です。
今回のテーマは「ドライマウス」についてです。
6月4日~10日は歯と口の健康週間でした。
高齢者だけでなく、若年層にも広がる口腔乾燥症(ドライマウス)。
厚生労働省の調査では、軽度を含めると65歳以上で約56%、65歳未満においても約35%の人が、口の乾燥を感じるという結果が出ています。
| ●ドライマウスの原因 |
ドライマウスの原因は様々です。
加齢による口のまわりの筋肉の衰えにより、咀嚼の回数が減少して唾液の量が減る場合もあれば、ストレス、よく噛まない食生活(舌を動かすことが少ない)などが原因になることもあります。
その他、飲んでいるお薬の影響で唾液が出にくくなったり、糖尿病・甲状腺・貧血などの病気の影響によることもあります。
シェーグレン症候群などの唾液腺の異常を引き起こす疾患などによってもお口の中が乾燥することがあります。
最近は、飲まれているお薬の副作用によるものと精神的ストレスによる方も多くみられます。
そして、ドライマウスは「ただ口が乾くだけ」ではなく、実は放置することでさまざまなトラブルや病気を引き起こす可能性もあります。
●ドライマウスになると
・・・・・・・・・・・・・
①虫歯や歯周病になりやすくなる
②口臭が強くなる
③口内粘膜がダメージを受け、口内炎が生じやすくなる
④食べ物を飲み込みにくくなる
⑤誤嚥性肺炎を引き起こしやすくなる(特に高齢者)
⑥食べ物の味を正常に感じにくくなる
⑦k是などの感染症を引き起こしやすくなる
➜リスクと解消法を知り、口内の健康を守ることにつなげましょう。
。 ▿.🦷・。▵.🦷。・。
| 🦷セルフチェックリスト |
|
✅3カ月以上、毎日口の中が乾く ✅顎の下がよく腫れる ✅乾いた食べ物を飲み込むとき水が必要 ✅水をよく飲む ✅夜中に水を飲むため起きる ✅乾いた食べ物が噛みにくい ✅食べ物が飲み込みにくい ✅口の中がねばねばする ✅口が粘って話しにくい ✅口臭がある
|
➜多くあてはまると、ドライマウスの可能性が高まります。
。 ▿.🦷・。▵.🦷。・。
| 🦷ドライマウスの治療法 |
治療としては、生活指導や対症療法が中心となります。
シェーグレン症候群や唾液腺疾患等の器質的な問題であれば医科と連携して治療が行われます。
| 🏥医療機関で治療する |
|
ドライマウスが重度の場合は、医療機関での治療が必要となることがあり、唾液代替製品や保湿ジェルなどが処方されることがあります。 また、必要に応じて、唾液腺の機能を改善する薬剤が処方されることもあります。
|
。 ▿.🦷・。▵.🦷。・。
| 🦷日常生活でできる対策 |
ドライマウスは多くの場合、毎日の ちょっとした工夫で改善が期待できます。
| ✨対策①唾液✨ |
|
①かむ力を育てる食事の工夫 唾液は食べ物を噛むことで自然に分泌が促されるため、噛む力は重要です。
②唾液を促す簡単マッサージと体操 • 耳下腺マッサージ:耳たぶの前を指の腹で円を描くようにゆっくりと押す
|
| ✨対策②保湿✨ |
|
①室内環境を見直す 意外と盲点になりやすいのが室内の乾燥で、口腔乾燥を助長します。
②飲み物の選び方 • 水や白湯をこまめに少量ずつ摂るのが理想的
|
| ✨対策③口腔ケア✨ |
|
①歯磨きのポイント ドライマウスの状態では、口腔内の自浄作用が低下し、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
②保湿ジェルや口腔用スプレーの活用 就寝中は唾液の分泌が少なくなるため、夜のケアは特に重要です。
|
歯と口の健康は全身の健康にも関係性が深いです。
自分の歯と口の健康についてあらためて考え、歯みがき習慣や食事習慣など、改善できる点があれば積極的に取り組んでみましょう!