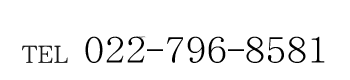春の気象病とその不調
こんにちは。仙台かわすみ産業医事務所です。
今回のテーマは「春の気象病とその不調」です。
春は日々の寒暖差や、低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わる気圧変動が大きい季節です。
寒暖差に対応するために、エネルギー消費が増えて疲れやだるさを感じやすくなります。
気象病の原因や自律神経について学び、春の体調不良を上手くケアしていきましょう。
| 🌸気象病とは |
昔から「季節の変わり目にはめまいがする」「天気が崩れる前には頭痛がする」「古傷が痛む」など、気象の変化によって持病が悪化することを”気象病”と呼びます。
春は日々の寒暖差や低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わる気圧変動の大きい季節です。
このような変化に対応するため交感神経が活発に働き、だるさや疲れやすさを感じたり、気分の抑うつや血圧の上昇、めまいや慢性痛の悪化などの症状が現れやすくなります。
。 ▿.🍃・🌸.🍃゜・。
| 🌸気象病はなぜ起きる |
気象病の原因は、気圧変動による自律神経の乱れです。
もともと人間は、ある程度の外部環境ストレスには耐えられるようになっています。
そのバランサーとして機能するのが自律神経です。
生活リズムが乱れたりしていると、自律神経が整いにくくなってしまいます。
気圧の変動は、耳の奥にある内耳が敏感に感知します。
内耳は三半規管や前庭など体のバランスを保つ気管が集まっている部分で、内耳が感じ取った気圧低下などの情報は内耳の前庭神経を通って脳に伝達され、自律神経はストレス反応を引き起こし、交感神経が興奮状態になります。
その結果、抑うつや、 めまいの悪化、心拍数の増加、血圧の上昇、慢性痛の悪化などの症状が現れます。
。 ▿.🍃・🌸.🍃゜・。
| 🌸自律神経セルフチェック |
|
✅ 乗り物酔いをしやすい
|
⇓
対策として、重要なのは天気や季節変化から受ける影響を少しでも減らし、痛みなどで体調を崩してしまう回数を減らすことです。
まずは自分が自律神経が乱れやすいかどうか、チェックしてみましょう。
あてはまる項目が多いほど、自律神経が乱れやすい傾向があります。
。 ▿.🍃・🌸.🍃゜・。
| 🌸春の体調管理のポイント |
| 🍴食事は欠食なく、バランスよく摂りましょう |
|
食事をとると、消化のために副交感神経が活発に働き、体はリラックスモードになります。 ★ 朝食は必ず食べる 特に朝食は、寝ている間に下がってしまった体温を上げ、自律神経を整えるのに大きな役割を果たします。 ※ビタミンB1 が多く含まれている食品:豚肉、うなぎ、玄米など
|
| 🏃こまめに体を動かしましょう |
|
軽い運動は積極的休養と呼ばれ、あえて体を動かすことで血流を改善させ、適度に汗をかくことで疲労物質を効率的に排出させることができます。 ・歩幅を広げる ★ ゆっくり長くできる運動をする 自律神経を安定させるために取り入れたい運動: ➜ゆっくり長くできるもの:なかでも水泳は自律神経の働きによい刺激を与えてくれます。
|
| 🛁入浴はシャワーだけではなく、湯船につかりましょう |
|
副交感神経が働き、自律神経のバランスが整います。
|
| 🛏睡眠をしっかりとりましょう |
|
体のダルさや疲れを溜めないためには、質の良い睡眠も欠かせません。
|
| 👕衣服で温度調節をしましょう |
|
朝晩と日中の寒暖差が大きいため、温度変化に体を適応させるために、
|
🌸ワンポイントセルフケア:耳のマッサージ
内耳の血流を良くしておくことで自律神経が整い、気象病の予防や改善につながるため、耳のマッサージが有効です。
両耳を軽くつまんで、上下横に5 秒ずつ引っ張ったり、耳を横に引っ張りながら後ろに回したりしてください。
春は気候の変化だけではなく、生活環境も大きく変化する時期です。
自律神経を整えて、春の不調を乗り越えましょう!