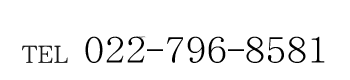職場でおこるハラスメント
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため集中的な広報・啓発活動を実施します。
ハラスメントといっても、種類は様々。
セクハラの件数は減少傾向も、パワハラやマタハラなどは増加傾向にあり、ハラスメントに対する知識と対策が必要です。
| ●職場でおこるハラスメントの種類 |
●パワハラ
・・・・・・・・・・
パワーハラスメント。
身体的・精神的に攻撃すること、など。
●セクハラ
・・・・・・・・・・・
セクシャルハラスメント。
性的な関係を強要すること、など。
●マタハラ
・・・・・・・・・・・
マタニティハラスメント。
産休や育休の制度を利用させない、など。
●モラハラ
・・・・・・・・・・・
モラルハラスメント。パートナーに対する暴言、など。
●ケアハラ
・・・・・・・・・・・
ケアハラスメント。介護休暇の利用をさせない、など。
●パタハラ
・・・・・・・・・・・
マタハラの男性版。
●逆パワハラ
・・・・・・・・・・・
逆パワーハラスメント。上司に対する暴言や暴力、など
その他、お酒の席などでのアルハラや、強すぎる匂いによるスメハラなどその種類は多数あります。
ハラスメントという概念は広がりを見せ、事業所の対策も一般的になっています。
多くの人が身近にハラスメント問題を認識している中でも、相談件数自体は増加傾向にあることから、
「無意識のハラスメント」が起こっているという可能性もあります。
パワハラなど、ハラスメントに該当する要素が周知 されやすくなった一方、そもそも定義を知らなかったり、ハラスメントとして該当しうる行為を具体的に知らないと無自覚なハラスメントの発生するリスクが高まると考えられるでしょう。
無意識なハラスメントに対しても適切に対応しながら状況改善を目指す必要があります。
。 *・〇・。〇。゜・〇・。* 。
| ●ハラスメントの要因 |
ハラスメントの発生の要因は、主に個人的要因と組織的要因の2つに分けられます。
|
●組織的要因:社員の会話量、労働条件や環境、組織文化、価値観など
|
↓
組織と個人は互いに影響し合っているため、要因が重なって発生することが多いと考えられます。
◆パワハラが起きやすい職場の共通点
|
45%
22%
21%
19%
13%
12%
12%
|
◆企業としての対策:
組織的要因への対応+実態調査・普及啓発・啓発・相談窓口の設置
|
●社員同士のコミュニケーション量に着目
●組織の文化や価値観に着目
●労働条件や環境に着目
|
。 *・〇・。〇。゜・〇・。* 。
| ♥加害者にならないために |
◆自分の常識が相手の常識と一緒という考えない
「自分の考えが必ずしも正解ではない」という意識を持って相手の気持ちや考えを確認しましょう。
◆指導時の注意
業務上必要な言動はハラスメントにはなりませんが、相手の気持ちを考えない一方的な言動はハラスメントとなる可能性が高くなります。
一方的に話すのではなく相手にも発言を促しましょう。
日々のコミュニケーションを増やすことも心掛ける必要があります。
◆ハラスメントについて勉強する
積極的に自分の情報をアップデートすることも大切。
。 *・〇・。〇。゜・〇・。* 。
| ♥被害者にならないために |
◆我慢しすぎず伝えることも必要
他者と関わる時はアサーティブコミュニケーション
(お互いを尊重しながら意見を交わすコミュニケーション術)が有効と言われています。
無理なこと、嫌なことを我慢しすぎず相手に伝えることも時には必要となります。
◆ひとりで悩まず誰かに相談しましょう
言葉にすることはメンタル維持に重要であり、落ち着いて客観視することもできます。
社内の窓口も確認しましょう。
そして記録をつけることが非常に重要です。
日時や場所、状況、言動を記録しましょう。